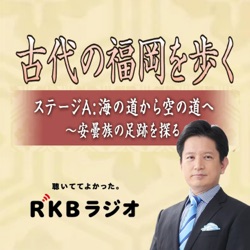Episoder
-
塩の道を青木湖、木崎湖と二つの湖を通って信濃大町に入ってきました。
ここにあるのが若一王子八幡宮。
ここには、神様と仏様が同居するという神仏集合がそのまま残っています。
正面の右の方の手前に三重の塔が、そして正面に観音堂が、左側に本殿があります。
本殿手前の方には赤い鳥居があるという、今では余り見られなくなった神仏習合の姿がここでは見られるのです。
そして、びっくりすのは本殿と本堂が廊下でつながっているのです。
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices -
安曇族の足跡を追って塩の道を辿っています。白馬村を少し入ったところに飯森神社がありました。
水神様を祀った神社だそうです。
この辺は水が涸れることはないけれど、水があふれて洪水にしばしば襲われる場所だそうです。
この神社の裏には広大な土地が広がり、遠くに山が見えます。
神社の拝殿、本殿を結んだ先にあるのが八方岳、そしてそこには八方池があり、神社の奥宮があって、例年、洪水にならぬよう地元の方はそこでお祀りをするのだとか。
案内人の田中さんの家も、以前は毎年頭ほどの大きさの岩を堤防の材料にするため川へ運んだのだそうです。
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices -
Manglende episoder?
-
塩の道に精通していらっしゃる白馬小谷研究社の田中元二さんの案内で、塩の道を糸魚川から少し入った南小谷から松本方面へと向かっています。
大変景色のすばらしい場所へ出ました。白馬村倉下という場所です。
松川という青く澄んだ水が大きな橋の下を流れています。
田中さんの話では塩の道のすばらしい点は、季節によって景色の色が変化することだそうで、上が白銀、下が桜のピンクだったり、新緑の緑だったり、変化に富むのが
すばらしいんだそうです。
確かに青みがかった川のずっと上には白銀のアルプスの山々がありました。
塩の道も、糸魚川から入ると、食文化、言葉、住まいなど「わずかな距離で変化していくのが面白い」ということでした。
※写真は白馬村倉下からの景色
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices -
今週から安曇族の足跡を訪ねて信州へ向かいました。
安曇族は、日本海を北上し、信州安曇野へ入っていって住みついたのだ、という説があります。
では、一体どこから信州へ入って行ったのか。
有力な説の一つとして新潟県糸魚川から塩の道、千国街道を通っていったのだ、という説です。
この説を検証するために塩の道を通ってみることにしました。
出発地は、糸魚川からちょっと入ったJR南小谷駅付近から。
案内を頼んだのは、塩の道に精通していらっしゃる白馬小谷研究社の田中元二さん。
田中さんが運転する車で通ってみることにしました。
距離的には、糸魚川から松本までは120キロの旅になります。
早速、百体の観音様が出迎えてくれました。
※写真は百体観音
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices -
安曇族の足跡を探るのに玉の話があります。
志賀海神社の歩射祭の時、射手士が勝間詣の沖津島に渡って行う神事で、海中に潜り海藻のガラモをとってくるという神事があります。
このガラモをとることが玉~潮満つ玉、潮干る玉をとってくる神事を表している、という見方をなさっているのが「神功皇后伝説を歩く」の著者、綾杉るなさん。
神功皇后の足跡を探っていますと、この玉の話がいろんな話しにでてきます。
神事としては北九州市の和布刈神社にも今に伝えられています。
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices -
安曇族の本拠地だったといわれる志賀海神社には数多くの神功皇后の話が伝えられています。
そこで、今週は神功皇后とは一体どんな人物なのか、海人族とのつながりを探っていきます。
話は「神功皇后の謎を解く」の著者で歴史家の河村哲夫さんに聞きます。
河村さんの話では、神功皇后は4世紀の終わり頃に活躍した人物で息長帯比売(おきながたらしひめ)という人物。琵琶湖の近くで産まれ育った人で釣りや海に潜水するのが好きだったのでは、ということです。
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices -
弓を射る行事、歩射祭が行われる前日にも行事が行われます。
弓を射る射手士は8人。
8人で100キロもある束にした俵~胴衣をかつぐ行事が胴衣舞という行事。
胴衣をかつぐのは新参という今年から参加した人。
たった一人で、神社から200メートル先の頓宮まで方にかつぐのですが、それを他の射手士が脇で支えながら、右に左にゆさぶりながら歩くのです。
この行事にはお囃子もついて歩きますから、射手士は歌も歌いながらかつぐのです。
この行事が終わって、午後から待ってるのが勝馬詣という行事。
本殿西の海岸、勝馬で海に入り海藻のガラモをとる行事があるのです。
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices -
安曇族の拠点となった所は福岡市の湾の入り口にある陸続きの島、志賀島だといわれています。
安曇族は、この島を拠点に玄海灘で船を縦横無尽に操り、主に朝鮮半島などとの交易を行ってきました。
この安曇族が信奉していたのが志賀海神社です。
この神社に伝わる祭りはいまでも、多少形は変わってはいますが、そのまま受け継がれています。
祭りは1月に行われる歩射祭からスタートします。
1回目はその歩射祭から紹介していきます。
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices -
今回は北九州市八幡西区の一宮神社から。
この神社の御祭神は神武天皇と天忍穂耳命。境内には古式の祭祀場が残されています。
磐境神籬を昭和になって復元したものということで、10センチ程の石が積み重ねられ直径1.5メートル程の円と四角の積み石塚が作られています。
大変貴重なものですが、これが自由に見学できるそうです。
シーズン9は今回で終わり、4月からは「古代の福岡を歩く ステージA 海の道から空の道へ~安曇族の足跡を探る」 が始まります。
かつて、志賀の島を拠点として活躍した阿曇族の足跡を探っていきます。
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices -
第14代仲哀天皇の妻である神功皇后は、謀反を起こした九州の熊襲を討伐するために天皇と下関にやってきます。
ここで討伐の為の拠点として豊浦宮を建てます。
その場所は現在の忌宮神社があるところ。
この近くの海で、神功皇后は干珠満珠の玉を手に入れたといわれます。
また、ここでは新羅の塵綸(じんりん)が皇后を襲うという事件がありました。
この時、天皇は自ら弓をとって敵を退散させました。
その勝利を喜んだ皇軍は旗をかざして塵綸の遺体の回りを踊り回ったそうで、現在もこれが「数方庭の祭り」として残っているのだそうです。
本殿の前には鬼石という石がありますが、そこが塵綸が葬られた場所だとか。
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices -
伊都国歴史博物館の王墓を紹介しましたが、ここには王墓以外の展示品もなかなか見応えのあるものも多いのです。
中でも面白いのは絵画土器です。
展示してあるのは深江城崎遺跡から出土した土器に描かれたクジラの絵です。
タテ40センチ程の土器の上の部分に、クジラが線で描かれています。
クジラの胴の部分に左右三本の銛も描かれています。
この土器と同じようなものは壱岐市の原の辻遺跡でも見つかっていて、同じく捕鯨の様子を描いたものと見られています。
クジラの絵の部分には矢印がつけてあり、よく観察できるように展示してあります。
※写真はクジラの絵を描いた絵画土器
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices -
西新町遺跡は早良区西新の修猷館高校を中心にした弥生時代~古墳時代初頭にかけての遺跡です。
西新町には現在でもリヤカーで商売される方が多く、庶民の町として大変賑わっている所ですが、この遺跡周辺もかつては日本各地の方、朝鮮半島からの方が集まり、大変賑わっていた様子が遺跡の出土品などから想像できます。
土器類は朝鮮半島系や畿内系土器、山陰系土器、瀬戸内系土器といった各地の土器が大量に出土しています。
中でも注目されるのは甑(こしき)。当時の日本列島では見られなかったものだそうで、穀物を蒸すという仕組みです。
竪穴住居にカマドがついて、さらに甑で料理され、蒸す料理の種類が増えると格段に料理の種類が増えたのではないでしょうか。
※写真は甑です。
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices -
伊都国の王墓を伊都国歴史博物館から紹介しています。
糸島の王墓を紹介しています。
三雲南小路遺跡、井原鑓溝遺跡ときて、最後は平原遺跡です。
この遺跡のポイントは大量の鏡が出土したことです。
中でも国内最大といわれる超大型の直径46.5㎝の内行仮面鏡は5面出土。
発掘調査を行った原田大六さんは、伊勢神宮の文献にある八咫の鏡に類似する鏡ではないかとみていらっしゃいます。
さらに、注目すべき点は、女性のイヤリング~耳璫(じとう)が出土、他にメノウ管玉、ガラス勾玉など女性用の装飾品が多いことから埋葬されているのは女性ではないかとみられていることです。
※写真は平原王墓復元模型
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices -
伊都国には三つの王墓があります。
古い順に三雲南小路王墓、井原鑓溝王墓、平原王墓とあります。
まず、三雲南小路王墓の展示品からみていきます。
この王墓は王と王妃の二つの甕棺が並んで出土しています。そして、副葬品も大変豪華です。
中でも注目されるのはガラスの璧や金銅四葉座飾り金具といったもので、中国の皇帝から下賜されたものではないかと見られています。
金銅四葉座飾り金具は中国では、位の高い貴族の木簡に使用されるものです。
ここでは甕棺であったため使用されず、甕棺の中に副葬されていたそうです。
※写真はガラスの璧
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices -
糸島には伊都国の王墓いわれる遺跡が3つあります。
三雲・南小路遺跡、井原鑓溝遺跡、それに平原遺跡です。
実は、これらの遺跡の様々な遺物を一堂に展示してあるところが糸島にあります。
伊都国歴史博物館といいます。
主に3階の展示物をじっくりみていきますと、糸島の王墓のことががよくわかります。
そこで、今週からこの伊都国歴史博物館の展示物を紹介していきます。
御案内は糸島ふるさとガイドの三苫節代(みとま・せつよ)さんです。
3階の展示室の入り口は大変こった作りになっていて、エスカレーターで上がってすぐ目の前に、糸島の山の風景が飛び込んできます。
海鳥の鳴き声も聞こえ、櫓の音もします。糸島半島に海から上陸する気持ちになります。
ここから王墓のいろんな出土品が目に飛び込んでくるのです。
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices -
今回は広い広い鴻臚館跡を歩きます。
大宰府の水城西門に通じているのが、かつて福岡市の平和台球場があった場所にあった鴻臚館東門です。
ここから大宰府水城西門に通じ、さらに大宰府政庁に通じていました。
従って、中国や朝鮮半島からのお客様は鴻臚館からこの道を通って大宰府政庁へと向かっていました。
元球場があった場所は広い原っぱがあって、見た目は何もありません。
しかし、ここを歩いてみると赤黒い線が見えます。
直線で50メートル程の線と70メートル程の線がありました。
これはかつての北館と南館の跡を印したものでした。
そして、北館と南館との間に少し低くなった部分があります。これが間の壕の跡。
橋もかかっていたのです。
詳しい地図は広場奥の鴻臚館跡展示館にいくとあります。そして、館内では発掘した状態の礎石や土器類もそのままの状態で見学できます。
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices -
水城の東門近くにやってきました。ようやく木樋がでてきました。
外堀に水を貯める導水管の役目を果たしたのが木樋です。
長さは土塁の下におよそ80メートルのわたって埋設されているのが確認されているそうです。
解説によりますと、木樋の幅は70センチ、厚さ26センチの板状に加工した底板材を⒉枚つないで鉄製のかすがいで留めたものだそうです。
いってみれば、⒉枚の板をホッチキスでとめたような物だそうです。
そして、左右に高さ80センチの側板を立て箱形にし、幅40センチ程の板状の木のふたをして埋めていたのだそうです。
この木樋は東門のすぐ近くで、復元したものを見ることもできます。
古代の福岡を歩くリポート
昨年5月末から、大宰府跡の蔵司地区にニホンミツバチの巣箱を設置して養蜂プロジェクトが行なわれています。
太宰府梅プロジェクトのひとつで、史跡地エリアで集めた蜂蜜の活用をめざす&環境学習の役立てる社会実証実験です。
NPO法人博多ミツバチプロジェクト理事長の吉田倫子(りんこ)さんに、いろいろ教えていただきました。
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices -
大宰府の水城跡を歩いています。
水城の内壕側を東門の近くまで歩いてきました。
木樋が見えるすぐ近くまできましたら、いろんなものがありました。
まず、瓦窯跡というのがありました。瓦を焼いた跡です。
8世紀中頃のものだそうで、ここでは登り窯ではなく、平窯を用いて瓦を焼いていました。
次にでてきたのが井戸の跡です。
木枠の井戸だったそうで、井戸の中から8世紀後半くらいの「水城」銘の墨書された土師器が出土したのだそうです。
東門近くには重要な出土品が多いようです。
古代の福岡を歩くリポート
令和発祥の都太宰府『梅』プロジェクトのひとつとして、昨夏、「令和の都だざいふ旅人の梅クラフトビール」が誕生しました。
梅酒系でもない、梅干し系でもない、想像を超えた梅の風味がさわやかなクラフトビールです。
ふるさと納税の返礼品にもなっている逸品。製造している(株)Four Starの代表取締役・前山和幸さんは生産拡大して多くの場所で売る気はないけど、「天満宮の『飛梅』の逆で、各地に太宰府の魅力を伝えるように飛んで行ってくれたら…」ともおっしゃっています。
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices -
西鉄下大利駅から南西にいきますと上大利地区があります。
ここにも老松神社があります。
ここに、水城跡もしくは上大利の小水城に使われたとみられる城門の礎石ではないかとみられる石が残っていることがこの程分かったそうです、この石は随分昔から置かれていたそうで、最近大野城市の教育委員会が確認したところ年代的にも664年に作られた水城と合致するといわれます。
大野城市の文化財にも指定されている貴重なものだそうです。
お参りのついでに捜してみてはいかがでしょう。
古代の福岡を歩くリポート
みやま市の九州オルレ・みやま清水山コースの7周年記念オルレが、2月17日(土)に行われます。
神宿る竹林をくぐり、女山の神籠石を眺め、清水寺を通り、道の駅みやまに向かう11.5km。
参加者にはいろんなおもてなしが用意されているそうです。
歩く時も、ガイドさんがついてくれるので安心です。
みやまウォーキング協会会長の丸尾敏朗さんにお話を聞きました。
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices -
JR水城駅のすぐ裏に小さな土手があります。この土手は「ててこじま」という伝承をもった土手です。
高さが2メートル、長さが50メートル程の小さな土手です。
「ててこじま」というのは父と子供を表す言葉です。
これは水城の土塁を作る際の伝説で、水城を作るためにもっこをかついで土を運んでいた親子が毎日毎日作業をしていたんですが、ある日、ようやくのことで完成に近づきます。
「できたぞー」という歓声の声が遠くから聞こえ、それを聞いた父と子は、力がぬけてかついでいたもっこをそこにほうりだしてしまいます。
まわりのみんなも次々と放り出した為、土が山となったそすです。
それが「父子島~ててこじま」と呼ばれるようになったという。
これは西門の方の伝説ですが、実は東門の方にも同じ伝説をもつ土手がありましてこれは「ひともっこ山」とよばれる土手です。
残念ながら東門のほうの「ひともっこ山」は開発のために今はないそうです。
古代の福岡を歩くリポート
毎年1月20日、みやま市の大江天満神社では国指定重要無形民俗文化財「大頭流幸若舞(だいがしらりゅうこうわかまい)」が奉納されます。
織田信長のエピソードが最も有名ですが、戦国武将たちがこよなく愛した幸若舞は、今ではみやま市にしか残っていません。
幸若舞保存会会長で第31代家元の大江地区への引越しを機に保存会に入って、今回5回目の舞堂出演の小川仁さんと、家元の松尾正春清継さんにお話を聞きました。
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices - Vis mere